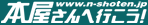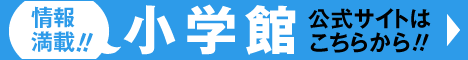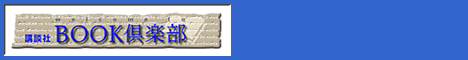抜本的施策策定を求める
「学校図書館の日」を記念してフォーラム「読書が21世紀の扉を開く−−学校図書館充実のための抜本的施策策定を求めて−−」(学校図書館議員懇談会、学校図書館整備推進会議主催)が六月八日午後二時から東京・神楽坂の日本出版会館で開かれ、出版、学校関係者ら●名が出席。
平成十三年度分の学校図書館図書整備費百八億円の完全消化を呼びかけ、「第二次学校図書館図書整備五カ年計画」施策策定と「子ども読書活動振興法」制定を求めた。
小・中学校の学校図書館の蔵書数を一・五倍に増やそうと、一九九三年より「学校図書館図書整備新五カ年計画」が始まり、総額約五百億円が地方交付税で措置。
「新五カ年計画」終了後も毎年約百億円の図書整備費が単年度予算として措置されており、今年度も全国学校図書館協議会や学校図書館整備推進会議などの諸団体の要望により百八億円が地方交付税措置された。
しかし、地方交付税は使いみちが限定されていないため、他の用途に流用されないよう各市町村で図書購入費として予算化される必要がある。
このため、日書連など三十六団体で構成する学校図書館整備推進会議では、国が付けた図書整備費予算化への働きかけを呼びかけている。
フォーラムの席上、学校図書館整備推進会議の笠原良郎代表は開会あいさつのなかで「教育改革の成功は学校図書館の充実なしにはあり得ない。
学校図書館整備のための中長期的な計画と国の施策を求める運動が必要」と述べ、運動の狙いとして平成十三年度の学校図書館図書整備費百八億円の完全消化単年措置ではなく、中・長期的な計画=「第二次五カ年計画」策定の実現を求める「子ども読書活動振興法」の制定を目指す−−に言及した。
また、全国学校図書館協議会の石井宗雄事務局長は「いま、なぜ学校図書館の充実か」をテーマに「平成十四年度から『調べ学習』『総合的な学習』などの新しい教育がスタートするが、そこで学校図書館は大きな役割を担うことになる」と話した。
このあと、「子どもの読書振興と政治の責任」をテーマに、学校図書館議員懇談会会長の河村建夫衆議院議員(自民)と同・事務局長の肥田美代子衆議院議員(民主)が講演。
河村氏は「各市町村が図書整備費を予算化するよう働きかけて、真の意味での学校図書館充実を図りたい。
司書配備については、司書が専属でやれる環境作りなど政治が果たすべき仕事はたくさんある」、肥田氏は「上野の国際子ども図書館完成、子ども読書年の決議、学校図書館図書整備費の地方交付税措置など多くの成果をあげてきたが、次は子ども読書活動振興法の成立を目標にしている。
子どもたちが図書館で生きる力、学ぶ力を蓄えられるよう整備充実を図り、本当の教育改革を実現した」と話した。
続いて、文部科学省の玉井日出夫大臣官房審議官が「文部科学省の学校図書館充実施策」をテーマに学校図書館充実への取り組み、司書教諭の養成・配置の促進、読書活動優秀実践校の表彰など同省の施策を説明し、ブックスタート支援センター事務局の白井哲代表が「ブックスタート運動の展開」として同運動が政官民の協力と地域社会の連携によって当初の予想を上回る規模で拡大していると話した。
また、書協の渡邊隆男理事長が「子どもの読書振興と出版界」をテーマに講演し、アジア圏全体で青少年の読書離れが進んでいると指摘。
教育は出版界が果たすべき役割と述べた。
最後に、中央教育審議会委員で渋谷教育学園理事長の田村哲夫氏が「新教育課程と学校図書館の課題」を記念講演。
田村氏は自分の力で考える「総合学習」の重要性を強調し、その舞台は教室ではなく図書館になると指摘。
図書館は本にこだわらずすべてのメディアを利用できる場になるべきと提案した。
東京組合の各種委員会編成決まる
東京都書店商業組合は六月一日の定例理事会で、新年度の各種委員会委員長と副理事長の担当委員会を決めた。
〈東京組合委員会編成〉◇総務・財務=萬田貴久◇組織=鳥井匡《丸岡義博副理事長担当》◇指導・調査=小泉忠男、《丸岡義博副理事長担当》◇経営・取引=五十嵐和秋《下向磐副理事長担当》◇流通改善=柴崎繁《奥村弘志副理事長担当》◇雑誌発売日=梅木秀孝《奥村弘志副理事長担当》◇出店問題=山口達郎《下向磐副理事長担当》◇事業=高原淳《奥村弘志副理事長担当》◇増売・共同仕入=神谷誠一《舩坂良雄副理事長担当》◇厚生=家田通久《丸岡義博副理事長担当》◇共同受注=新倉信《舩坂良雄副理事長担当》◇出版物販売倫理=大橋信夫《丸岡義博副理事長担当》◇読書推進=越石武史《舩坂良雄副理事長担当》◇再販研究=岡嶋成夫《下向磐副理事長担当》
「こどもワールド」全国3会場で開催
日販の「本と遊ぼうこどもワールド2001児童図書展示会」が、七月から名古屋、鹿児島、東北の三会場で開催される。
各会場では「日本にやってきた『世界の絵本たち』」などテーマごとにコーナーを設けて約五万点の図書を展示。
人形劇、スタンプラリーなど子どもと本との出会いを広げる楽しいイベントを用意する。
「読み聞かせ」「ファーストブック」について関連書コーナーと読み聞かせイベントを一層充実させるほか、地域の社会児童施設に図書の贈呈式も行う。
会場と日程は次の通り。
開催は午前十時から午後五時まで、入場無料。
▽名古屋会場=7月21日〜23日(明治生命名古屋ビル16階)▽鹿児島会場=8月3日〜5日(鹿児島卸団地組合会館)▽東北会場=8月18日〜20日(岩手県産業会館大ホール)
東映配給映画「ホタル」に出資
日販は一九九一年から映像ソフトの制作・買い付け、国内外での諸権利取得などの版権ビジネスを展開しているが、五月二十六日から公開されている東映配給映画「ホタル」にも出資を行っている。
「ホタル」は、一九九九年六月に劇場公開し日販も出資した映画「鉄道員(ぽっぽや)」の主演俳優とスタッフ、製作メンバーが再集結した作品。
日販は「鉄道員」が邦画史上でも出色の成績を収めていることなどを踏まえて出資を決定した。
日販ではこれまで劇場公開作品を含めて約百五十タイトルに出資しており、「Shallweダンス?」「失楽園」などヒット作が多数出ている。
マガジンフェスタで広告大賞の授賞式
角川書店は六月五日午後六時からホテルオークラで「角川マガジンフェスタ2001」を開催し、「エリア読者が選ぶ角川広告大賞」東日本地区の授賞式とパーティーを行った。
この賞は全国各地で展開されている雑誌広告を広く紹介するために昨年創設されたもので、今回は選考委員の選出による「特別部門」を設けず、すべて読者からの投票のみで選考された。
対象となった媒体は十三誌で、このうち東日本地区は『東京ウォーカー』『横浜ウォーカー』『千葉ウォーカー』『北海道ウォーカー』『シュシュ』『ザテレビジョン』『月刊ザテレビジョン』『ミセスザテレビジョンしってる?』の八誌。
式典で角川歴彦社長は「ブランド力とは何かといえば、他のものと差別化でき、読者満足度が高いということで、ワールドワイドに展開できる雑誌はスーパーブランドといえる。
ウォーカーやテレビジョンはアジアへ展開できるという自信を得た。
今後の展開を楽しみにしていただきたい」とあいさつした。
サイト連動型情報誌
メディアワークスは七月十日、国内最大のオンライン・ショッピングモール「楽天市場」を快適に利用するオフィシャル・マガジン『楽天マガジン』(月刊)を創刊する。
体裁はA4変型判・一三六頁、定価税込み五百円、発行部数二十五万部。
「楽天市場」は契約企業六千九百、商品数八十二万点を誇るショッピング&オークション・サイト。
会員数二百万人、月間アクセス数は二億三千万ページビューにのぼる。
七日に行われた記者発表会で、メディアワークス佐藤辰男社長は「今まで任天堂、ソニーと組んでゲーム雑誌を出してきたが、今回、三木谷社長にお願いして新しい雑誌を出す。
ネット社会の数少ない成功パターンが楽天市場。
巨大なショッピングモールは多層的で奥深い。
雑誌ならではの提案ができれば意義があると確信している」。
楽天市場の三木谷浩史社長は「雑誌は前から出したかった。
総合メディア企業の第一歩として、インターネット・ショッピングに特化した雑誌ができるのではないか。
八十万扱い商品の中から厳選した商品を紹介してプッシュしていけば面白い」と、雑誌のコンセプトを語った。
『楽天マガジン』は二十代後半の女性をターゲットに据え、「安い、お洒落、かわいい」商品を紹介していく。
紹介する全商品にアクセスナンバーを表示、購入の便を図るほか、読者限定の「福袋」に記載されたパスワードで割引購入できるなどの仕掛けもある。
足で調べた舞台裏
本紙に「注目的新刊」を好評連載中の斎藤一郎氏が遊友出版から『本屋なしではいられない』を発売した。
四六判・二五六頁、定価本体千二百円。
第一章が「本の雑誌」の連載をまとめた「本屋さん観察学」、第二章が「注目的新刊」で取り上げた実用書をジャンル別に整理した「本屋で趣味を見つけよう」、第三章の「出版営業奮戦記」は本紙「斎藤一郎の本屋さん大好き」の連載に加筆したもの。
スリップとは何か、カバーのかけ方、書店の看板などの普段目に止めない書店の仕事や日常を、暖かい視線で見つめる。
一周年のプレゼントキャンペーン
ブッキングとビズシークが運営する「復刊ドットコム」は、サービス開始から六月一日で一周年を迎えたのを記念して、三十日まで一周年プレゼントキャンペーンを実施している。
復刊ドットコムは、ユーザーが自分の復刊したい書籍をウェブサイト上で投票するという国内初のECサイト。
復刊希望が百票を超えた書籍について出版社、著者と復刊交渉を行い、復刊した商品をサイト上で購入できる。
現在までに二万人以上のユーザーが三千四百点の本に投票しており、総投票数は四万三千票に達する。
この結果、二十七点の復刊が実現している。
プレゼントキャンペーンは全ユーザーを対象に、サイト上で応募する形式。
ソニーのノートパソコンやデジタルカメラ、復刊書籍などの商品が当たる。
URLは、http://www.fukkan.com/present/
本屋のうちそと
返品が多い、減らしてほしいと取次さんから何度も言われる。
返品が多いと人件費、運賃がこんなにかかると表まで作ってくれたI島さんありがとうございます。
さて返品を減らすために何が問題なのか考えてみた。
1、取次の問題まずランクの設定、何でこの本とこの本が同じランクなの?疑問だらけだ。
セット商品の送り込みはやめてほしい。
2、出版社の問題勿論結果としてだが売れない本が多すぎる。
新刊点数も多すぎる。
もう少し吟味して出してほしい。
営業マンは注文だけ取るのではなく、どうやって売るのかまで話せるようにしてほしい。
3、書店側の問題売るつもりで入れたが、残念ながら返品売れると思って追加したが、時遅く泣く泣く返品のように誰もが納得する返品もあるがその本が売れるか売れないかなど考えない返品もあるのだ。
自分以外の人(上司、前担当)が注文したので返品その部門の棚に大きくて入らない、小さくて奥に行く、サイズが合わないので返品新刊とわかっていても棚がきついので常備入れ替えで一緒に返品その出版社または担当者が嫌いなので返品品出しが終わらないので、左はじの数冊を返品理由はないがその本を売りたくないので返品まだまだありそうだがこのへんにしときましょう。
これを読んだ方、返品減少運動にぜひご協力ください。
(たに)
新会長に鈴木康弘氏
東京都書店商業組合青年部は六月五日午後三時から文京区の東京ガーデンパレスで第11回通常総会を開催し、新年度の事業計画を決めるとともに、新会長に鈴木康弘氏(世田谷区・優文堂)を選任した。
総会は吉田圭一氏(吉田書籍部)の司会で進行。
安藤弘会長が「出版不況が続く中だが、青年部は昨年も永六輔氏の講演会、再販集会などで頑張って活動してきた。
新年度も書店の現場に立ち、現場の意見をアピールしていきたい」とあいさつ。
正副議長に原田福夫(信愛書店)、上地進二(千歳書店)両氏を選んで議事に入った。
昨年度活動報告では■期末の会員数が十一名減の百九十九名になった、■青年部ホームページを開設し、FAXネットに変わる会員相互の意見交換の場になった、■TS選書委員会は名称を「掘り出し選書」に変え、ルートサービスを利用してローテーションさせる、■ポイントカード制の導入を跳ね返す運動を行う−−などの取り組みが報告された。
TS流通協同組合の活動は同組合片岡理事長が「読者が求める本を早く確実に届けるため、独自の仕入れと物流、決済システムを確立した。
出版社九十三社と直取引しているが、百五十店の参加店のうち五月の利用店は七十六店と半数程度。
発注金額も二百五十万円前後に停滞している」とし、積極的なシステム利用を呼びかけた。
また、扱い出版社の拡大については、当面三百社を目指して、二百社と継続交渉していることを明らかにした。
会員からの質疑では、公正競争規約の見直し、新古書店対策、CVSの早売りなどについて取り組みの要望があった。
役員改選では理事二十八名、監事二名を承認し、初理事会で会長に鈴木康弘(優文堂書店)、副会長に渋谷眞(四季書房)、三浦実(三成堂)の各氏を選出した。
鈴木会長は「不況が続く中で、書店の課題を議論していき、魅力ある、注目される青年部にしていきたい」と就任のあいさつ。
このあと、東京組合萬田理事長が「東京組合と青年部は二段ロケット。
力を併せて目標に到達したい」と祝辞を述べた。
−無題−
居酒屋に行き「とりあえずビール!」と叫ぶ人が多いとみえて、外国人の中にはとりあえずというブランドビールがあると思っている人もいるらしい。
さて、ビールの後は酒か焼酎か、ここは何かと意見の別れるところである。
『薩摩焼酎奄美黒糖焼酎』(柴田書店MOOK、千五百円)は九州全域ではなく、鹿児島の焼酎にこだわる。
日本酒といえば清酒を指すが、焼酎だって日本酒である。
県の東、大隈・鹿屋から錦江湾をぐるり回って南薩、さらに甑島(こしきじま)列島、種子島などの大隈諸島、奄美諸島までを十二地区に分けて、五十一の酒造を紹介する。
幻の焼酎として知られる「森伊蔵」はかめ壷仕込み。
味が落ちるので大量生産ができない。
奄美諸島でしか造られていない黒糖焼酎は、サトウキビの黒糖が原料。
「里の曙」、「碧い海」、「朝日」などがある。
旨い肴と一緒にこれらの焼酎が飲める店、乙種焼酎には血栓予防の効用があるという教養講座。
また、焼酎の歴史と文化や製法のルポなど、薩摩焼酎のうんちくが盛りだくさん。
東京、大阪で買える酒店や酒造のホームページアドレスもある。
『幻の酒造を訪ねて日本名酒紀行』(サライムック、小学館、二千円)は北海道旭川市の「男山」から、熊本県山鹿市の「千代の園」まで四十五の酒造を訪ねる。
東京ではただ一つ、武蔵村山市の渡辺酒造「吟雪」が紹介されている。
狭山丘陵に近いこのあたりは、江戸時代から多くの造り酒屋があった場所。
秩父の清麗な伏流水があったのである。
杜氏の制度が確立したのは江戸中期の頃。
村から十人位で出稼ぎに行く。
杜氏は酒造りの頭で、人事権や給料分配権を持っていた。
こちらも全酒造のデータとホームページアドレスが、巻末に詳しく紹介されている。
この二冊のムックが並んでいる書店はほとんどない。
片方があっても、料理書の隅だったりする。
焼酎、清酒の酒造とも最近は女性が進出していて、料理書の棚で構わないのかもしれないが、やはり棚は違う。
だからといってクルマ雑誌の隣も勘弁してもらいたい。
酒と肴、日本の伝統食は、お弁当の本とは分けておいて欲しいものである。
(遊友出版斎藤一郎)
−無題−
鈴木康弘氏略歴昭和28年1月1日生れ、48歳。
東京都出身。
昭和49年3月、中京大学体育学部卒。
59年、世田谷区・・優文堂入社、現在BBS店店長。
平成10年6月から東京組合青年部副会長。
スキー指導員の資格を持つ。
−無題−
スリップへのバーコード印刷について/日本図書コード管理センター事務局長/久保田実出版物(雑誌除く)へのコード表記場所は、本の一番外側(オビを除く)、奥付、スリップの3箇所となっています。
本の一番外側は取次で商品仕分け、書店で売上の登録に使用されています。
奥付は主に図書館で書誌情報の整理に使用されます。
スリップは出版社では売上統計や報奨券の集計作業に、取次では補充注文書の読取り集計に使用されています。
スリップの読取機は非常に高速で速いものは毎分2000枚以上の読取能力があります。
それだけに読取機の価格も相当高価で高いものはソフト込みで2億円、安いものでも2000万円程度いたします。
スリップのコード表記をバーコードに変更した場合、現有の機械で双方同時処理が可能なのか、設備を更新しなくてはならないのか、当然相当長期(多分バーコード表記が90%に達するには5年以上かかると思われます)にわたって混在して送られるスリップの処理が不経済にならないか等を勘案して、業界内で相談して基準を決めなくてはなりません。
個々の出版社が単独で決められる性格のものでないことをご理解ください。
当センターでは本年度の事業計画として、出版物(雑誌を除く)のコード表記の再検討を行うことにしています。
その内容は現在の「OCR-B」と「バーコード」の双方を機械読取可能な印刷が義務付けられているがこれは必須事項であるのか。
バーコードの印刷位置が指定されているがそれは必要なのか。
スリップの仕様をどのようなものにするか。
などが検討対象となります。
これらの結論が出るまで今しばらくお待ちいただきたく存じます。
なおごく一部にISBNそのものの使用を拒否している出版社、バーコードは使用しないという出版社があることを申し添えます。
「本読む子がイジメの標的」にショック
五月三/十日号の週刊文春に出版界の最前線で活躍されている方々の座談会が掲載されていました。
その中で大手書店のTさんという方の「近頃の小学校では本を読む子がいじめられている」という発言があり、私は大いにショックを受けました。
イジメそのもののあることは否定しませんが、「本を読む子供が……」というのは、どのような状況でどのようにいじめられているのか、きちんと状況を説明すべきだと思います。
一部の学校や出版界の崩壊を原因とされているようですが、それがどのように本を読む子同士のいじめにつながっているのか。
このような問題は曖昧にすべきではないと考えますし、少しでも優しい心をと店の一部を開放して子供に読み聞かせを行っている書店もあるわけで、何十万、何百万のベストセラーに癒されるような問題でもなかろうと思います。
コンビニが撤退し始めた
私の書店は交差点の角にある。
最近、北側にあるコンビニが廃業した。
二年ほど前開店した店だった。
また西側にあるコンビニは、経営者が経営権を他人に譲った。
さらに、西に安売りショップがあったが、大型のラーメン店に替わった。
全国紙の報道によると、コンビニの経営環境が悪化している。
ファーストフードの店が安売り攻勢をかけているため、コンビニの主力商品である弁当などの食べ物が売れなくなったようだ。
コンピューターで売れ筋の商品を管理していても、別の業種に競り負けするのだ。
これからの時代は、健全で体力があり、競争力が強い書店が生き残れる。
これは、当然のことだ。
そして、私が望みたいのは、書店業界の安定的な繁栄だ。
お客さんに迷惑をかけない堅実な発展だ。
日本経済が変遷しても、それに合わせられる知恵を身につけたいと私は思う。
読み聞かせらいぶらりい
ぬいぐるみのくまさんのおなかって気持ちよさそう。
そういってくまのおなかに、魚、ネコ、犬と次々にはいっていく。
「えーっ、ムリだよ」という子どもの声も気にせず、とうとうゴリラもはいってしまった。
色も絵もあたたかな気分にさせてくれる。
このもようだあれ
おはなしの間に、ちょっと一息、という時にこのしかけ絵本はおススメ。
縦長のスマートな本を開くと、ページいっぱいにかかれた不思議な模様。
「おやおや、だれかかくれているよ」とヒントを読む前に、元気な声で答えがかえってくる。
チキチキチキチキいそいでいそいで
物置でみつけた腕時計のネジを回すと、チキチキいそいで、と鳴りだした。
あわててコウくんは走りだす。
家の人も、隣のチエちゃんにもうつって、とうとう街の人達も走りだす。
タコだって海の中を走っちゃう。
テンポよく、リズムにのって、読み手もつられて走るように読んじゃった。
『出版クラッシュ●』に反論
『出版クラッシュ●』(安藤哲也、小田光雄、永江朗の各氏共著、編書房発行)が昨年発売されたので拝読した。
書店に対し辛口の批評が書いてあり、最初は書店に対する愛のムチかとも思った。
しかし、どうも私の考え方とずれており、考え方を明確にしたく投書させていただいた。
以下、数項目に対し反論を述べさせていただく。
「書店の不良債権は少なくとも一千億円ぐらいあり、これを解消する手段は再販制と委託制を止めること」(三六頁)……書店の不良債権の大部分は大型書店が借り入れによって分不相応な拡張を行い、これを取次が支援したことに起因する。
これを解消するために一般書店に大幅に影響する再販制や委託制をなぜやめなければいけないのか。
経営を誤り、多額の不良債権を作った書店は自己破産するなど自己責任で解決すべきではないか。
再販制については公取委に提出された意見のうち九八・八%が再販制度存続であったが、著者から再販制度解消の意見が出てくるとは驚きである。
委託制の解消についても健全な中小書店に犠牲を強いて、バブル的拡張で失敗した大型書店やそれを支援した取次を救済することにならないか。
そもそも書籍はヒットするかどうかは店頭に並べてみなければわからない要素をもっており、出版した社の社長だってヒットするか否かは発売前にはよくわからないのではないか。
このような背景により委託制が定着しているのではないか。
委託制をやめれば、小出版社は注文の形をとらなければ取次に納入できなくなり、営業が書店を巡って番線印を押してもラウおねだりをせざるを得なくなり、その結果衰亡の途をたどることになろう。
「書店業界はぬるま湯であり、書店が再生するには経営者の再教育が必要である」(一一四頁)……経営者の失敗は自らの財産の喪失につながるものであり、経営者は常にこれを念頭に置いて行動している。
いったいどんな再教育をしようとしているのか。
著者は、家業として経営している中小書店は退場し、企業として経営している大型書店やチェーン店が生き残ればよいと考えているのかもしれぬが、家業としてやっている書店にも生きる権利はあるのである。
「日書連は機能していない」(一一五頁)……他を誹謗するには具体的事実を記さねばならないと思う。
なぜ機能していないと言われるのか不明である。
日書連もこのように書かれているからには抗議すべきではないか。
書店業界を色々調査研究され、事情に詳しい小田氏に対して敬意をもっているが、今回は鼎談という形をとったため勇み足が過ぎたのではないかとも思いますが、いかがですか。
週刊売行き情報
都条例改正で不健全図書の区分陳列方法が示された。
幾つか方法があるにせよ注文しない本が入荷する現状では出版社側による完全ビニール包装を求めるしかない。
(ぺ)(1)『新しい歴史教科書』扶桑社4‐594‐03155‐2……13冊
(2)『チーズはどこへ消えた?』扶桑社4‐594‐03019‐X……12冊
(3)『ティアリングサーガユトナ英雄戦記オフィシャルプレイヤーズバイブル』エンターブレイン4‐7577‐0484‐4……6冊
”『パスワード龍伝説』講談社4‐06‐148558‐X……6冊
(5)『十二番目の天使』求龍堂4‐7630‐0106‐X……5冊
(6)『南紀潮岬殺人事件』祥伝社4‐396‐20717‐4……4冊
”『あなたはひとりじゃない』光文社4‐334‐97298‐5……4冊
”『ベイブレード爆転スピンアップbook』小学館4‐09‐102861‐6……4冊
(9)『ハリー・ポッターと秘密の部屋』静山社4‐915512‐39‐8……3冊
”『ハリー・ポッターと賢者の石』静山社4‐915512‐37‐1……3冊
”『地名で読む江戸の町』PHP研究所4‐569‐61548‐1……3冊
”『愛をもらって』星雲社4‐434‐00889‐7……3冊
”『鯨の哭く海』祥伝社4‐396‐63187‐1……3冊
”『竹中教授のみんなの経済学』幻冬舎4‐344‐90003‐0……3冊
”『楯』文藝春秋4‐16‐357650‐9……3冊
”『姥ざかりの花の旅笠』集英社4‐08‐774530‐9……3冊
”『壷中の天』講談社4‐06‐182165‐2……3冊
(6月4日〜10日調べ)
週刊売行き情報
ananに連載、大橋歩の銅版画イラスト入りで村上春樹の新刊となれば売れぬ筈がない。
当店で6位にランクイン。
一つ一つのエッセイが読んでいて気分がいい。
(隆)(1)『市販本新しい歴史教科書』扶桑社4‐594‐03155‐2……33冊
(2)『チーズはどこへ消えた?』扶桑社4‐594‐03019‐X……17冊
(3)『十二番目の天使』求龍堂4‐7630‐0106‐X……15冊
(4)『市販本新しい公民教科書』扶桑社4‐594‐03156‐0……11冊
”『聞き取り書き取りCD付英語は絶対、勉強するな!』サンマーク出版4‐7631‐9388‐0……11冊
(6)『村上ラヂオ』マガジンハウス4‐83871‐314‐2……10冊
”『なぜか、「仕事がうまくいく人」の習慣』PHP研究所4‐569‐61488‐4……10冊
(8)『多摩らび〓16』けやき出版4‐87751‐142‐3……8冊
”『01年下期版間違いだらけのクルマ選び』草思社4‐7942‐1061‐2……8冊
(10)『英語は絶対、勉強するな!』サンマーク出版4‐7631‐9338‐4……7冊
”『みんなの経済学』幻冬舎4‐344‐90003‐0……7冊
”『新・魔獣狩り(7)鬼門編』祥伝社4‐396‐207197‐3……7冊
(13)『恋するために生まれた』幻冬舎4‐344‐00086‐2……6冊
(14)『バターはどこへ溶けた?』道出版4‐944154‐35‐6……5冊
”『スター☆ガール』理論社4‐652‐07197‐3……5冊
”『センティメンタル・ブルー』講談社4‐06‐182185‐7……5冊
(6月3日〜9日調べ)
−無題−
編集部から「声」欄に皆さんからの投稿を歓迎します。
原稿は八百字以内にまとめ、住所、氏名、店名を明記の上、編集部「声」係へ。
紙上匿名はできますが、筆者のわからない原稿は掲載できかねます。
趣旨を変えずに文章に手を加えることがあります。
採用分には薄謝を進呈します。
〒101−0062東京都千代田区神田駿河台1−2全国書店新聞編集部「声」係=03−3295−7180Eメール=●
サン・ジョルディ
☆近所に、小さな小さな書店があります。
女性の店主さんは、上品で穏やかで、いつでも実家に帰った時のような雰囲気で迎えてくれます。
そして何より、本について詳しく、本を愛してらっしゃる。
そのため私はいつも、デパート内の大きな書店を通り過ぎて、その店に足を運びます。
こんな本屋さんがもっともっと増えたら幸せですね。
〈上尾市/36歳/主婦〉
☆10代、20代の多感な頃、夢中で本を読みました。
悩みをなくす答えが欲しくて本を読んで様々なことを考えました。
本はいろいろなテーマを投げかけ、物事を多面的に考える力を養ってくれました。
心を鎮める豊かな時間を与えてくれました。
本を読むことは受動的な体験かも知れません。
でもそこから得る様々な知識は、日常生活からは発生しないだろうものもたくさんあります。
本屋さんは宝の山そのものです。
これからも宝をもっと見つけたい!〈安中市/39歳/主婦〉
支えとなった一冊☆妊娠24週で子供を死産で亡くし、精神的にも肉体的にもボロボロだった頃のこと、「16週あなたといた幸せな時間」(向井亜紀・著)を主人がプレゼントしてくれました。
母であった証しである母子手帳とこの本は、私の一生の宝です。
あの時、ボロボロの私を救ってくれてありがとう。
〈熊本市/30歳/専業主婦〉
SJでプレゼント☆サン・ジョルディの日、4月23日には私は孫たちに図書カードをプレゼントすることにしています。
子供、孫ともに、私の影響で小さい時から読書が大好きで、おもちゃより本を買い与えてきました。
本を読むことによって、いろんな世界へ旅したり、いろんな世界のことを学ぶことができたりする。
これからも読書の夢は尽きません。
〈姫路市/65歳/無職〉
☆10年以上前から、「サン・ジョルディの日の本と花の市」の様子を写真に収めたしおりを愛用しています。
遠い外国の習慣ですが、昔から憧れていて、4月になると友人たちとイチオシの本を贈り合ったものです。
これからもこのしおりと一緒に大好きな読書を続けていきたいと思います。
〈江別市/22歳/パート〉
もっと宣伝しては☆「世界本の日サン・ジョルディの日」というのは聞いたことはありますが、具体的にはよく理解していません。
本屋さんは大好きで、ほぼ毎日行っています(今の会社と同じビルにあるので)。
以前は企業内図書館で働いていました。
書店さんから、「本屋は儲からない」という話を聞いたことがあるので、なるべく本は本屋さんで買うことにしています。
もっと「本を読もう、買おう」キャンペーンを大々的にやるべきだと思います。
頑張りましょう。
〈横浜市/26歳/自由業〉
☆チョコレートを贈る日や、そのお返しの日。
お返しの倍率まで人々の脳裏に植え付けた業界の宣伝の凄さに比較すると、「サン・ジョルディの日」は心もとなく思っております。
もっとマスコミを巻き込む話題作りが必要でしょう。
中学生になり異性を意識するころ、誰でもが好きな人に恋文をそっと挟んだ本を贈る。
そういう習慣を不思議と思わない雰囲気になったらいいと思わずにはいられません。
勿論、その本はマンガでも一向に構わないと思います。
〈千葉市/67歳/無職〉
本屋さんのパソコン活用パート2(12)
<個客管理ということ>本屋の仕事を管理面から観ると、お客樣管理と商品管理(仕入・在庫・販売)と資金管理の順に優先管理され、そして三つの管理の土台である書店人育成が、お店のリーダーの仕事ではないでしょうか。
特に個客管理は商売の根幹でしょう。
一度、お店の固定客が幾らぐらい買って下さっているか測ってみてはいかがでしょうか。
例えば、外売で500人、月平均売上@2000円とすると月商100万、店売では500人で月3回来店@1000円なら500人×3回×1000円で月商150万です。
合計250万円の月商をこの1000人のお客さんが保障してくれているのです。
ポイントやプレゼントはこのようなお客さんにこそ差し上げたいものですね。
(ポイント制は集客活用が注目されるが、小書店では個客差別化やお友達になれて感謝的活用が効果的かも)この1000人のお客さんとは親しいでしょうし顔も見えるでしょう?このお客さんを喜ばせ楽しませ感動してもらう方法なら思いつけそうですね。
目的は現場からの発想で具体的に見つけましょう。
山積する業界問題(ポイント制や新古書店の著作権や販売権問題等)を自店の業務にどう関連づけ実務改善に結びつけていくか。
お客さんの視点に立つことは実務の管理業務としては個客管理の視点になります。
その素になるデータが個客データです。
外商での個客管理には基礎的な管理側面と応用的な側面(本来の管理目標だが)があります。
基礎的な側面とはどの顧客に何を幾ら売り回収したか?という取引データを素にした配達カードや納品書・請求書発行や販売集計データの表示といった売掛金管理的な側面です。
販売集計を顧客分析と広告するソフトもありますが、増売を可能にする顧客分析でも個客管理でもありません。
CMやPRのフレーズで勝手なイメージを作らないように自分を訓練するのもメディア・リテラシー@情報リテラシーです。
<市販外商ソフトの限界>先回の「外商管理ソフトで楽々管理」で使われているソフトは琵琶湖湖畔の書店さんが自店用に自作されたモノを、8人の書店人が書店の外商業務に使い勝手を良くし、基礎的な管理に応用的な活用法を加えて、改良され続けているソフトです。
それでもすべての書店現場に100%フィットするわけではありません。
現場活用の部分が各店で違うためそんなソフトは作成不可能です。
現場活用の部分を創るのは現場の書店人の仕事なのです。
今入手できるパソコンは、ソフトもハードも工業製品としては半完成製品で、使用者が常に面倒見てやらなければ使えないモノです。
いつもエンストする車のようなものです。
それでも使うかは利用者個人の意見の分かれるところですが、ここでは「それでも使う」という立場で、比較的安定して作動し利用者の都合でいつでも変更修正でき、人の発想により近いエクセルという表計算ソフト(Ms-EXCEL)のシート(巨大な縦横表用紙)を使います。
ソフトの使い方は別個に前もって習熟する必要は在りません。
やりだせば身体が事前に覚えていきます。
習うより慣れろ、です。
<個客管理の目的>一人当たり月平均5000円とか目標を創ります。
お客さんは何故本を買うのでしょうか?なぜあなたの店から買うのでしょうか?(逆に言うと何故他の店から買うのでしょうか?)個の問題の説明仮説から情報収集項目が決まります。
<記録項目とその柔軟的変更>情報にも賞味期限ともいえる命の長さで長期と短期があります。
1、まずは属性。
例の個客管理シート・モデル参照。
2、取引情報。
いつ何を誰が買ったかの情報ですが、間違っても書名をISBNコードだけで記録しないで下さい。
活用には役に立ちませんから。
書名や著者は記録されるでしょうしそれなりに活用も出来ますが、できれば「個人の興味」という視点で、購入動機や独自の内容分類のタグ(検索する場合のキーワード)を付属させて下さい。
活用ではこのタグや分類の多様性が威力を発揮しますから。
3、個客宅を巡回するでしょうが、フィールド情報も収集する。
店からの全体地図を張っておき、工事やビル、空き家、新規オープンのお店、気の利いた散歩道、季節を楽しませてくれる花の見どころ、など。
後日その時々の基準で検索して活用するためのデータウェアハウスです。
<管理活用ツールとその実験>シート例を各店の各担当者なりに創られて実際に使ってみる、その結果を本連載の読者諸氏どうしで話しあいましょう。
変わり続ける購買行動に常にフィットさせていく工夫は出来るだけ多くの人と交換しあうことが、活用法の自分なりの開発にも情報リテラシーを高めるにも不可欠なのです。
(甲川純一)
サン・ジョルディ
2001「世界本の日サン・ジョルディの日」キャンペーンの一環として実施した雑誌出版社との共同企画「お薦め本特集&共同懸賞」(五十三社・百二十九誌協賛)には、ハガキ応募が九千五百八十五通、インターネット応募が二万二千四百八十三通、合計三万二千六十八通が寄せられ、そのほとんどにサン・ジョルディ、読書、書店に対するメッセージや、「心が揺れた一冊」への思い入れが書き添えられていた。
この中から読者の生の声を一部紹介する。
本屋さんのパソコン活用パート2(12)
外商を考える連想キーワードと参考文献<個客管理ということ>=かけば帳、輪島の朝市でのおばあちゃん、江戸の貸本屋。
サバイバルを支えるお客数;損益分岐売上から損益分岐個客数。
<市販外商ソフトの限界>=システム設計者と現場書店人のジョイント、習うより慣れろ。
<個客管理の目的>=目的を現実的に自ら設定。
借り物の知識(呪縛)からの自由。
<記録項目とその柔軟的変更>=情報の価値づけとライフ・サイクル。
<管理ツールとその実験>=永遠なる実験。
各担当者のコラボレーションを。
<個客シートの活用法のアイディア>=ワクドキ、仕掛け、人の輪。
◎最近とみに流行しているインターネット通信販売〜ウェッブ書店〜の意味や実務は、木下修+星野渉+吉田克己『オンライン書店の可能性を探る』日本エディタースクール出版部2001年3月刊A5判180P巻末「主なネット書店一覧」3Pに詳しい。
◎個人オンライン書店の開店奮闘記は、北尾トロ『ぼくはオンライン古本屋のおやじさん』風塵社2000年9月B6判203Pが好書。
個客シート活用法のアイディア◇活用法1>個客購買・支払い状況の把握と売掛回収の早期化策◇活用法2>拡売商品の見込み個客リスト作成へ◇活用法3>個客と商品単品のリンクで「お勧め本リスト」の作成配布へ。
◇活用法4>お客さん同士の出会いを創るノウフー・ヒューマン・ネットワークのインターチェンジャーへの途へ。
外売は個客の生活場面に密着した販売シーンで、もうそこまで来ている高齢化対応社会には重要な販売チャネルになります。
日販損益計算書
(単位百万円)売上高七六一、〇五一売上原価六八二、〇九五売上総利益七八、九五六販売費及び一般管理費六六、四九七営業利益一二、四五八営業外収益一、二〇一受取利息三五九その他収益八四二営業外費用九、六三一支払利息五四一売上割引八、九五四その他費用一三五経常利益四、〇二九特別損失三、〇七五税引前当期利益九五三法人税、住民税及事業税二八法人税等調整額四五四当期利益四七〇前期繰越利益四七九再評価差額金取崩額三〇九当期未処分利益一、二五九
経常利益40億円に
日販の第53期(平成12年4月1日〜13年3月31日)決算概況がまとまった。
売上高は前期より〇・三%減の七千六百十億円で三期連続減収になったが、返品率の改善による営業費の減少や、営業拠点の統廃合など管理費の削減で販売管理費が二・六%減少。
これを受けて営業利益は二・三%増の百二十四億円、経常利益は四十億円と過去最高の利益を計上した。
これに特別割増退職金支払いや有価証券評価損など特別損失三十億円を計上し、当期利益は四億七千万円となった。
売上高の内訳は書籍が二千五百十四億七千七百万円(四・一%減)、雑誌三千九百二十四億五千九百万円(二・一%増)、開発商品千百七十一億千四百万円(〇・六%増)で、返品率は書籍三七・八%(一・七ポイント減)、雑誌二九・九%(〇・六ポイント減)、開発商品四・五%(〇・四ポイント減)。
六日に行われた記者発表で日販柴田常務は「前期は損失処理により当期利益が大幅な赤字となったが、今期は当初目論んだ通りの成績を上げられた。
新中期経営計画ネオステージ21にとって54期が正念場。
気を引き締めていく」と述べた。
特別損失三十億円のうち早期退職に応じた社員の特別割増金は十六億円強。
期末の社員数は前期より二百九十三名減って、二千二百七十七名となった。
増床は五百十八店、四万七百八十一坪、減少は五百五十八店、二万八千九百四十九坪。
また、小会社十三社を含めた連結決算では、経常利益六十一億円、当期利益十六億円となった。
−無題−
講談社機構改変1、企画室を解消し、web現代編集部の業務をデジタル事業局デジタルコンテンツ部に移管する。
2、学芸局と学術局を統合し、学芸局とする。
3、学芸図書第一出版部を現代新書出版部、学芸図書第二出版部と学芸図書第三出版部を統合し学位芸図書出版部、科学図書出版部をブルーバックス出版部と改称する。
4、総合編纂局と辞典局を統合し、総合編纂局とする。
5、総合編纂局(A)を総合編纂第一出版部、総合編纂局(B)を総合編纂第二出版部、総合編纂局(D)を総合編纂第三出版部、総合編纂局(C)を総合編纂第四出版部と改称する。
6、総合編纂局に辞典出版部を新設し、辞典局(A)と辞典局(B)の業務を移管する。
7、デジタル事業局デジタルマーケティング部とインターネット直販部を統合し、デジタルマーケティング部とする。
8、キャラクター事業局と国際室の業務の一部を統合し、ライツ事業局とする。
9、キャラクター事業局映像・ソフト製作部を解消し、その業務をライツ事業局ライツ管理部とデジタル事業局デジタルコンテンツ部に分掌する。
10、ライツ事業局に国際ライツ管理部を新設する。
11、国際室の業務を社長室、ライツ事業局国際ライツ管理部、書籍販売局書籍第二部に分掌する。
12、国際室ニューヨーク駐在事務所を社長室に移管する。
13、営業企画室に総合受注センターを新設する。
14、営業企画室の業務の一部を販売促進局販売企画推進部に移管する。
15、販売促進局販売促進統括部の一部を社長室に移管する。
16、販売促進局販売促進第一部、販売促進第二部の担当地区を一部変更する。
17、販売促進局販売サービスセンターを解消し、その業務を営業企画室総合受注センターに移管する。
18、宣伝局読書推進事業部を広報室に移管する。
19、業務局書籍業務部と書籍製作部を統合し、書籍業務部とする。
20、書籍販売局店頭総合推進部を解消し、その業務を書籍販売局と販売促進局販売企画推進部に分掌する。
21、書籍販売局特販企画部を解消し、その業務をライツ事業局キャラクター事業推進部、雑誌販売局、コミック販売局、書籍販売局に分掌する。
22、広告局広告業務第一部と広告業務第二部を統合し、広告業務部とする。
23、広告局広告企画制作部を広告制作部と改称し、業務の一部を広告総務部と広告営業推進部に分掌する。
初のオール太洋会
太洋社の取引書店で組織する全国六地区の太洋会が東京に集結して八日、目白のフォーシーズンズホテル椿山荘東京で「オール太洋会」が開かれた。
永六輔氏の講演、各地太洋会総会、販売研究会に続いて午後四時から行われたオール太洋会の総会は、司会の塚原孝英氏(LIC英林堂)が昭和四十年、熊本で発足した九州太洋会以来の六太洋会の歩みを紹介。
九州、東海、北陸、四国、東北の各太洋会会長のあいさつに続いて、太洋社安丸常務が「青森から鹿児島まで百数十名の書店を迎えて開催した。
二十一世紀を迎えて会のやり方を変えようと初めて六つの太洋会が一同に会した。
昨年四月から本年三月まで増売コンクールを実施したところ、トータル四百店舗の会員で前年比九九・一%だった。
この数字は業界全体の九七・四%より一・七ポイント高く、会員の努力に感謝している」と述べ、増売コンクールの表彰式に移った。
入賞は朝日新聞社など七社の出版社賞、店売部門(A、Bコース)、外販部門(前・後期・総合)で、トータルのポイントを競う会別では関東太洋会がトップ。
九州、東海、北陸、四国、東北の順だった。
午後五時半からの懇親会であいさつした関東太洋会太田博隆会長(ブックスフジ)は「昨年、各地の会長、太洋社とも相談してオール太洋会が実現した。
昭和四十年から五十五年の間に六つの会ができたが、北海道、近畿も参加してもらえればと考えている。
デフレ、閉塞感の中だが、暖かいご支援を」とあいさつ。
太洋社国弘社長は「太洋社は今月末が決算だが、五月までの数字で前年を割っていない。
残りわずかだが、全力を尽くしたい」と述べたほか、アメリカのサウスウエスト航空が無駄のない経営で二十八年連続黒字となっている話を紹介し、「出版業界の無駄は返品。
三月のムック発行点数は九百点あり、四月のムック返品率は五四%になった。
無駄な返品コストを見直したい。
今回、ウェブサイトを使った新情報システムを発表する。
できるだけ書店に導入してもらい、販売を活性化していきたい。
先代から伝わる『お客様あっての太洋社』の理念で頑張っていきたい」とお礼を述べた。
翌九日は文京区水道の本社で「すいか祭り」を開催。
地方書店も多数出席して、web受発注のデモや、読み聞かせ会の提案、出版社と活発な商談が行われた。
新客注システム稼働へ
大阪屋友の会連合大会が六月六日、浜松市・舘山寺温泉「ホテル九重」で開かれ、会員書店百五十九名、出版社百三十名、大阪屋十六名など総勢三百二十八名が出席した。
総会は午後五時から同ホテル・コンベンションホールで冨士原純一幹事(冨士原文信堂)の司会、山口武司兵庫地区幹事長(文進堂書店)の開会の辞で始まり、田村定良連合会長(田村書店)が「消費不況は日々実感しているが、この数か月、一誌当りの部数はある程度安定してきた感じがある。
書籍も販売の仕掛けやメディアに乗れば売れる。
書籍、雑誌とも読者の情報をつかめばまだ売れるのではないか。
しかし、今年のゴールデンウィーク中、雑誌の入荷は二日氏かなかった。
目の前にお客がいるのに鮮度の高い商品がないのは疑問だ」と問題提起。
「売れない根性がしみついているが、お客に買わす根性で不況を乗り切ろう」と積極販売を呼びかけた。
議案審議では、役員改選で田村幹事長を再選したほか別掲の副会長と総務・経営・増売委員長を承認。
新任の毛利元治総務委員長(毛利書店)が事業報告を行い、子ども読書年を記念して関西一円十九会場で実施した「えほんと子育て講演会」に千名を越える参加者があったこと、増売取り上げ商品などを報告した。
会計・監査報告を承認したあと、大阪屋鈴木一郎社長が祝辞。
鈴木社長はまず第54期の決算について「売上げは一千億円をキープでき、前期とほぼ同程度の売上げ。
昨年末、新書店請求システムを稼働させたことにより、書店からの返品入帳処理を例月二十七日まで繰り上げたことが要因の一つ。
損益面でも前期並みを確保できた」と発表した。
また、関西ブックシティの機能強化、IT化時代にふさわしいネットワーク確立、全天候型オープンシステムの拡大というインフラ整備の課題について「iブックシティを活用した新客注システムを七月一日から本格スタートする」と紹介。
出版社に対してはデータ提供の協力と、大型連休においても出庫業務の協力をお願いしたいと注文した。
出版社を代表して講談社保月滋常務は「社内のOA化、書店ネットワーク、KBCの受注システムなど革新の姿勢に期待を持っている。
成功企業は基本的マーケッティング戦略がしっかりしている。
出版業界も読者に近いところの戦略提案が重要だ」と述べ、一例として「雑誌は全国同時発売をできるだけ早くと考えている」と発言した。
日書連今西英雄副会長は萬田会長のメッセージを代読したあと、各県組合に加入していない友の会会員がいることを指摘し、「組合で一緒に業界の改善を目指そう」と訴えた。
友の会連合会役員会長=田村定良(田村書店)副会長=春名貞夫(奈良・サン書房)、山口武司(兵庫・文進堂書店)、本間昌治(京都・ブックス新教京都)、上野山順士(和歌山・上野山書店)、平岡賢二(鳥取・本の店ひらおか)、内藤文雄(広島・中央書店)、本久善一(高知・明文堂)、関口実(茨城・セキグチ書店)2デイ納品めざす大阪屋友の会の懇親会であいさつした大阪屋三好専務は、七月に稼働する「新客注システム」について、「今週からモニター店でテストが始まっている。
十二万点、百万冊の在庫がリアルタイムでわかり、追跡システムもある。
従来の3デイ到着から2デイになる。
午後一時までの受注は、当日出荷、翌日書店着。
条件は特別正味で従来とは別の出荷。
契約いただければ、iモードより画面の大きいドコモの端末エキシーレを無料配布する。
六月下旬に発表する」と説明した。
−無題−
◇日本実業出版社(5月25日付、○新任、◎昇格)代表取締役会長中村洋一郎代表取締役社長上林健一取締役(業務統括)鈴木雅夫同(編集統括)○橋本裕之同(メディア統括)○乗松幸男同(経営統括)○西澤一守監査役五十嵐和夫広告担当(役員待遇)小林良彦出版担当(同)田中大次郎営業担当(同)◎吉渓慎太郎渉外担当(同)辻本静男国際担当(同)小倉進大阪担当(同)上田勲*取締役特別顧問の赤木頌一氏は退任。
◇日貿出版社(5月30日)取締役会長高橋幸重代表取締役社長○水野渥取締役(営業部長)○臼杵務津夫同(非常勤)大野利夫監査役小澤實樹*桑原俊博代表取締役社長は病気治療のため辞任。
◇全国教科書供給協会会長○政本公男副会長平松正典同○手塚弘三理事(企画調査委員長)○今井直樹同(業務研究委員長)○高野隆同(渉外広報委員長)○今泉良郎同鈴木勲同横瀬庄次同熱海則夫同小林一也同上野久徳同村越正則同佐藤美小王同和田征士同○鶴英男監事○星野孝平同○大曽根奎介同永島公朗相談役○森實事務局長祖父江昭一